環境の大きな変化で認知症に2(入院、配偶者喪失)
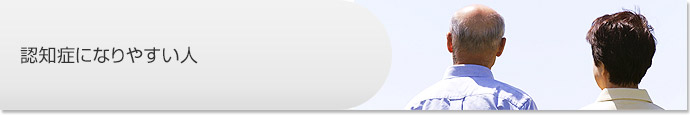
環境の大きな変化で認知症に2(入院、配偶者喪失)
フレディ松川先生の研究・書籍を参考に、認知症になる「きっかけ」として、環境の大きな変化や大きなストレスなどの要因を見てみます。
※だからと言って必ず認知症になるということではありませんので、誤解なきよう。
一般的な予防の参考としてお読み下さい。
高齢での入院で体力や認知力を奪う
長期の入院は、高齢者の体力や認知力を奪うことがよくあるようです。
「入院」という急な環境の変化
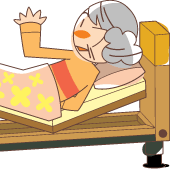
まず、入院による急な環境の変化ということです。
認知症の人とは限らず、今まで特に問題がなかった高齢者の方でも、「入院」という大きな変化をきっかけに認知症の症状が現れたり、進行したりする場合があるようです。
突然入れられた見慣れぬ部屋(病室)、見知らぬ病院のスタッフ、そんな急な変化の中で本人は「ここはどこ」「あなたは誰」の状態に陥ってしまい、不安や苛立ちから、混乱したり大声を出すなど不穏な状態になったりすることがあります。
入院した当時は、本人にとっては、それまで馴染んでいた環境が急に失われ、混乱と緊張の中にいることでしょう。
入院生活で体力を奪われる
次に、入院生活で体力を奪われるということです。
入院が長期化すれば、運動不足から体力が低下します。筋肉・体力が落ちて衰弱が進むと、やがては命にかかわる状態になります。
毎日同じことの繰り返しで活気や刺激のない状態が続いて脳の活動が停滞すると、当然ながら認知力が低下し、本人のリハビリに対する意識もなくなってしまい、ますます衰弱することもあります。
「寝たきり状態」というのは、それだけで体力を奪っていきます。もちろん個人差はあるでしょうが、1週間寝たきりで20%、5週間では50%かそれ以上の筋肉が落ちてしまうといわれています。
逆に、退院できて元の生活に戻れた場合には、いくらか状態が回復することもあるようです。
認知症の点でも体力の点でも、入院生活は、治療と引き換えに高齢者の生命力を奪っていくことにつながる可能性があるようです。
入院生活で自分でものごとをしなくなる
入院している期間は、当然ながら病院のスケジュールに沿って生活し、それまで自分で管理していた薬も病院側が管理してくれます。このことは、少なからず高齢の患者本人にとって良いこととは言い切れないようです。
自分で薬などを管理するとからには、記憶したり思い出したり、ある程度の緊張感を保って脳を使おうとするはずですが、入院といういう環境がそれをしなくてよい状況にしてしまうためです。
してもらうことに慣れてしまうと、やがて自分でしようという気が失せてしまい、それまでの習慣も放棄してしまうことがあるようです。
体も脳も、使わなければ退化していくことになります。
病気や疾患など、あらゆる事情があって入院しているに違いないのですが、高齢者の入院はできるだけ短くすることが、本人の体力・気力、脳活動を守ることにつながるようです。
配偶者を失った夫が認知症や癌になるケース
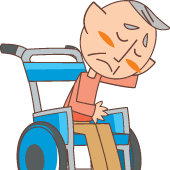
特に男性の場合、配偶者の死によって、その変化やショックに耐え切れずにストレスを抱え、認知症や癌になってしまうケースが多いといいます。
まずは、愛する配偶者を失った悲しみ、喪失感に襲われることです。
次に、例えば、食事から衣服の世話まで妻任せであった夫は、妻の死によって激しい環境の変化を経験します。やったことのない家事を始めますが、当然全てこなせるわけではなく、ストレスを抱えていきます。
また何をするにも人任せだった場合、妻を失ったときに何をしたらよいかわからなくなって、暗中模索の日々を送ることになります。家庭内依存が高い場合です。呆然とした生活を送り、認知症へと進んでいく可能性があります。
こうした状態を防ぐには、少しでも自分のことは自分で行う習慣をつけるしかないと言われています。
また夫は、妻が自分より先に亡くなるとは思っていないため、心の準備ができていないので、そうなったときの衝撃があまりにも大きいとも言われています。一般に高齢者の場合、妻が亡くなってから3年以内に夫が亡くなるというケースが多い、と言われているようです。
筆者の父の場合

筆者の父のお話をすると、父は妻(筆者の母)に先立たれて2年半後に亡くなりましたので、まさに上記のケースだったのだと思います。
父が妻を失ったときにショックはあまりにも大きく、「これから自分はどうやって生きていけばいいのか」と声を大にして叫ぶほどでした。それまでも認知症(たぶん軽度)だったのですが、妻の死後、ショックと混乱の中で一気に認知症の症状が進行したように見えました。
実際に、以下のようなことが増えました。
- 同じ話を繰り返す頻度がそれまでは1時間に2~3回程度だったのが5分に1回ぐらいになった
- (薬の副作用もあったのでしょうが)急に怒り出したり激高したりする
- 今言っていたことと正反対のこと、あるいは人が言っていたことを最初から自分が言っていたことのように言い放つ
- 感情の起伏が激しくなって話の脈絡がなくなる
- 短気記憶が著しく低下した
- 「周りの人がグルになって自分を管理しようとしている」と思い込む被害妄想的な状態(実際に本人には内緒で、ケアマネージャーたちと見守り体制を行っていたのですが、それを察した本人は、自分がボケ老人扱い・病人扱いされていると思い、プライドを傷つけられたという強い怒りをいだきました)
やがて、それまでしていた散歩もしなくなり、何度かマッサージのために通ったデイサービスも知らないうちに辞めてしまい、1日中テレビの前に座って思い悩んだりボーっとしている毎日になりました。そしてヘルパーさんによくもらしていた言葉が「早く(亡き)妻のもとにいきたい」だったのです。
そんな生活が続いた2年半後、父はガンで亡くなりました。
気持ちの問題を解決するのは、結局は本人(筆者)
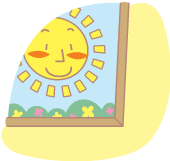
筆者の父のお話の続きです。父に対しては、以下のようなことを何度言ったかわかりません。
- 少しでも散歩した方がよい
- もっと人のいるところへ出た方がよい
- マッサージを受けるのでも何でもいいから、他人と接した方がよい
- 小さなことでも、何か好きなことを見つけてやってみたらよい
しかし、当の本人にその気がなければ、周囲がいかにせっつこうが何も行動には結びつきません。筆者は、自分のそれまでの配慮の足りなさや努力の不足を痛感するとともに、気力・気持ちの問題は、結局本人が気づいたり変えようとしない限り変わらないものだ、と思いました。
父の例をとれば、認知症の症状として「意欲を失ったり考えがまとまらない」ということがあったと思います。そんな状態の中で自分を見つめなおしたり、変えていこうとするのは無理なことだったかもしれません。それは仕方のないことだったのでしょう。
そこで私たちに視点を移してみると、だからこそ、将来私たちが高齢者になるときまでに、自分の気持ちを切り替えたり保ったりする習慣をつけておくこと、適度な運動をしてなるべく多くの人や物に触れ、脳を活性化させる練習をしておくことは、やはり必要です。
それが、私たちの老後の生き方を決めていくことであり、私たちの子供世代に介護の重い負担をかけないことへとつながると思います。
![認知症の症状が家族に出たとき、あなたはどう対応しますか?[認知症の窓]](https://xn--n4x78da08sj80b.com/wp/wp-content/themes/ver01/img/common/title.gif)
